みなさん、こんにちは。
「来年4月から増員します!〇〇〇人増員ですから、よろしく!」留学生が増え続けている昨今、この様に収容定員の増員を敢行する日本語学校が増えています。
しかし、現場で一生懸命働いている先生や事務員にとっての増員はそんな簡単なことではありません。現場の教員数や事務員数が潤沢であれば良いのですが、経営側はそんな事お構いなしです。
現場を無視した無理な増員は、経営側と現場の軋轢を深め、次第に現場が悲鳴を上げてしまい、後々離職者が大量に出てしまうことがよくあります。
そんな状況になるのに何故増員するのか?単に定員増をすれば収益増加、経営者が金儲けに走っているだけだ!と言う単純な話でもありません。そこには日本語学校という特殊な業界が抱える収益構造上の問題があるのです。
今回は増員と日本語学校が抱える収益構造上の課題について、私自身の経験を踏まえながら詳しく解説していきたいと思います。
何故増員が必要なのか
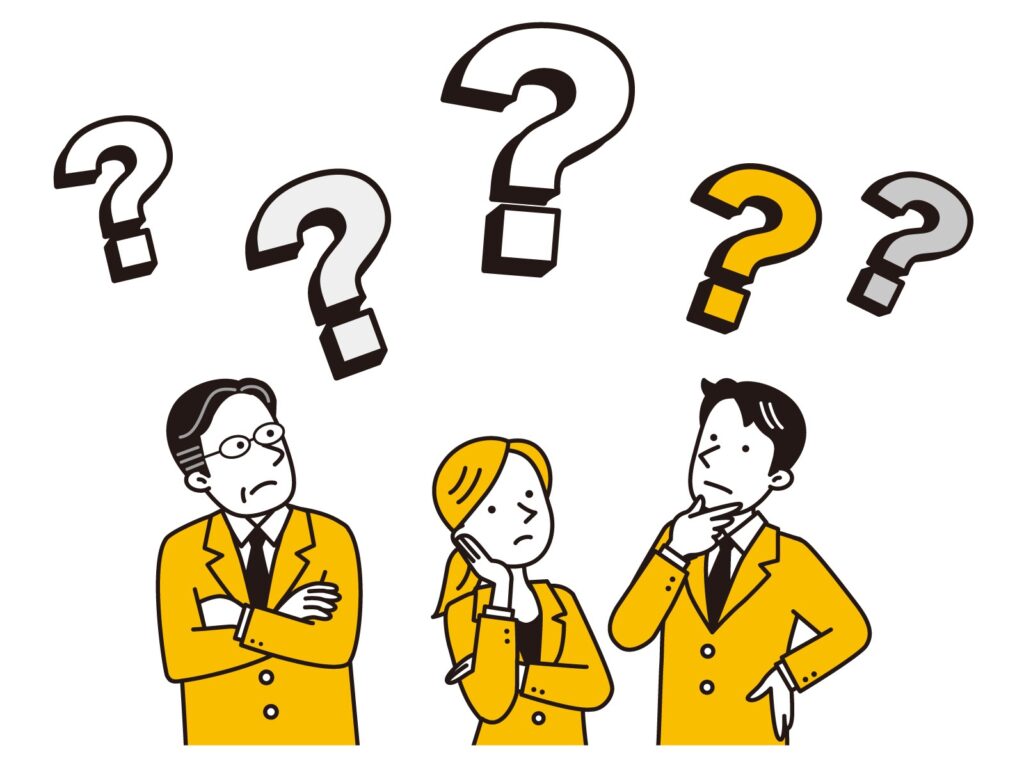
増員が必要な理由は幾つかありますので、よくある事例を交えて以下に記載します。
初期投資費用の回収のため
日本語学校を設立する為の開校資金は、おおよそで2000万円から4000万円程度が必要とされています。現金一括で払っていれば問題ないのですが、銀行から借り入れをしている経営者も多くいます。
日本語学校は文部科学省の認定を受けなければ開校ができません(以前は法務省)。まず文科省に認定申請をするため、校長、教務主任、生活指導担当者を必ず雇用し、お給料を支払わなければなりません。
文科省への認定申請から開校許可(認定日本語教育機関)を貰った後わ、第1期生が入学するまで約10ヶ月から一年、この約1年半の間、日本語学校は無収入状態で且つ人件費や地代家賃等の支出が出続けます。
また、文科省の認可も1回目で貰えるとは限らず、不認可とされてしまうとさらに1年程度無収入の状態が続きます、不認可になると初期投資の2000-3000万円のお金も底をついてくるわけです。
そうすると、初期投資のお金はかなり多いのにも関わらず、収入が入ってくるのが遅く、さらに文科省から不認可となってしまうと更なる支出が必要となります。これでは初期投資の費用回収は容易ではありません。
これこそ経営者が増員に踏み切る最たる理由です。投資した費用を少しでも早く回収するには増員をして、売上を増やすことが1番早いからです。
入学希望者全員にビザが出るわけではない(売上見込みが読めない)

これは全ての日本語学校が抱える悩みの種です。残念ながら、入学を希望する全ての方にビザが出る訳ではありません。ビザが出なければ、日本に入国することができません。
そうなると、基本的な収入が留学生の納める学費しかない日本語学校にとって、ビザが不許可で入学キャンセルとなってしまったら、お金が入ってきません。
更に2019年〜2022年にかけて、留学希望者の多い発展途上国の国々(ネパール、ミャンマー、スリランカ、バングラデシュ等)のビザ許可率が1-3%になった時期がありました。100人のビザを申請して1人しかビザが貰えない状況に陥ったのです。
当時、東京入国管理局の管轄下にある首都圏の日本語学校は軒並み大変な収入減となってしまいました。更には2019年末からコロナの流行で入国禁止処置が取られた事により、約2年半の間、新たな収入が皆無の状態になりました。
残念ながら、2019年〜2022年の3年間で倒産、廃校になってしまった日本語学校がかなりありました。特に小中規模の日本語学校の廃校が相次ぎ、日本語学校経営の厳しさを痛感しました。
この様にビザが不許可になったり、疫病や自然災害発生により入国、入学が出来ない事態が発生し、収入が減少するリスクと常に隣り合わせの状態です。
ですので、そもそも日本語学校の経営は常に不安定であり、不安定な収益構造をどのように乗り切り、適正な経営ができるかがキーポイントなのです。
蓄えが出来る時に蓄える必要がある
不安定な日本語学校経営だからこそ、収益を上げられるチャンスがあれば、その時に最大限の投資を行い、来たるリスクに備えて最大限の売上獲得を目指す、この投資こそが増員です。
無論、備えなければならないのは、ビザの不許可や疫病、自然災害だけではありません。
給与や賞与のベースアップ
これは避けて通れません。かつて日本語学校の給与ベースアップはほぼ皆無、賞与あればラッキーの学校がほとんどでした。
しかし、今は日本語教員を筆頭に基本給は大幅にベースアップされ、基本給30万円超えの学校も珍しくありません。ちなみに、私が日本語学校に入った当時、手取りは18万円くらいでした……当時は本当に厳しい時代でした。
教職員の給与ベースアップや賞与増額をする事で当然人件費も増額します。どの業界も同じですが、人件費は最も高い支出です。
また、人件費は毎年上がっていきますので、社員の給与や賞与の事を考えると、増員による増収増益を狙う事は必然とも言えます。
設備投資の必要が出てくる
全国に日本語学校は700以上ありますが、その中でも最新気鋭の設備と建物を備えている日本語学校は、一部の大規模学校を除いて非常に稀です。
私が働いている日本語学校もそうですが、設備はお世辞にも最新気鋭とは言い難く、最低限の設備と建物修繕を施した程度です。これは多くの日本語学校にも同じ事が言えます。
そうなると、建物や学内設備の修繕やICT機材の導入(タブレットやモニター、プロジェクター等)等の追加設備投資の必要性が出てきます。
特に大規模修繕や移転等が発生するとかなりの費用がかかってしまいます。この設備投資の点においても、増員による増収増益の必要である事が言えます。
増員の前に経営者は現場を見よ

上記では増員の必要性について、日本語学校の収益構造や経営の脆さ等のリスク、人件費や設備投資をはじめとした収益分配の観点から解説しました。
しかし、増員とはあくまで現場の教職員の日々の働きがあって、初めて実現出来る事を経営者は知らなければなりません。残念ながら、現場をきちんと理解している経営者はほとんどいないのです。
人が足りなければ雇えば良いではない
経営者の口癖ナンバーワン、教員足りないなら雇えば良いじゃん?これを口で言うのは簡単ですが、ただてさえ人手不足の日本語業界、教員募集がどれだけ大変かは現場を見なければ分かりません。
また、採用活動もかなりの労力を使います。誰でも雇えば良いという訳ではありません。組織にとって合わない可能性の高い人を採用してしまうと、組織の崩壊にも繋がりかねず、慎重に進めなければなりません。
100人増やしたら、クラス数は5クラス以上増える
もし、100人増員したら最低でも4-5クラス、日本語のレベル分けを厳密にやるなら5クラス以上を新たに開講しなければなりません。
小学校や中学校等とは違い、日本語学校は1クラス最大20名までしか入れることができません。仮に5クラス開講したら、新たに5クラス分の教員を当てがわなければなりません。
▶️1クラス:1日/4コマ×5日=20コマ
▶️5クラス:1日/20コマ×5日=100コマ増
▶️専任教員:最大1週間24コマまで
(但し、最大コマ数で入ると授業以外の業務時間が全く取れない)
▶️専任だけで5クラス増員に対応するためには新たに5人の専任が必要
▶️非常勤講師、専任教員の採用に失敗したら、クラスが運営できず違法な状態になる可能性がある
上記の様に単純に教員を雇えば良いなんてことは絶対にありません。経営者が現場の声に耳を傾けなければ最終的に組織が危機的な状況に陥ってしまうのです。
教員だけでなく、事務員も疲弊する
多くの日本語学校には、日本語教員の他に留学生の生活サポートや入管業務を遂行する事務員がいます。事務員がいなければ、全てのサポートを教員がやらなければならず、事務員の存在も非常に大きいのです。
当然ながら、100人増えれば学生サポートや入管業務も100人分増えてしまいます。そうなると今までの様な業務の進め方では確実に行き詰まってしまいます。
また、増員を意識する余りに学生募集の入学条件を甘くしてしまうと、質の悪い学生が多数入学してきます。この質の悪い学生のサポート、管理で更に疲弊してしまうのです。
最後に
今回は日本語学校の経営者、経営陣の方々に必ず知って頂きたい現場のこと、現場側に知ってほしい経営者側の悩みやポイントをご紹介しました。最後に最も大切な事を以下に記載します。
経営者と現場が一致出来るかが最大のポイント

増員は現場に多大な負担増をもたらす為、私も含め、増員はあまりしたくないのが本音です。ただ、経営および運営の事を考えると、増員も致し方ないと言わざるを得ません。
その為、最も大切なことは、経営者側も現場側も双方がコミニケーションを密に取り、双方が納得した上で、経営者が常に現場の大変さを知り、理解してから増員に臨むことです。
日本語学校職員の方であれば、現場の辛さは誰もが分かると思います。いつも辛いのは現場職員です。その事を経営者が理解出来なければ、経営側と現場の乖離は酷くなり、必ず組織運営が行き詰まります。
その点を経営者が理解すると同時に、経営者側が増員をしたい理由について、現場側も理解しなければなりません。そして、経営者はその事を明確に説明しなければなりません。
双方がお互いを知り、一致して進めていければ日本語学校としての力強さが生まれてきます。組織力の高い日本語学校は、これから先に起こる難局も乗り越える事ができます。
本記事が多くの日本語学校経営者、日本語職員の方に届き、増員に関わるお悩みや疑問解決のお役に立てたら幸いです。


